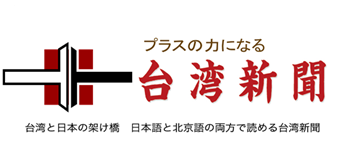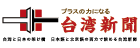【東京採訪報導】第27回参議院選挙が7月21日に投開票が行われ、124の改選議席と非改選の東京選挙区の欠員補充を合わせ全125議席が確定した。与党自民党は改選議席が39に激減し、連立与党の公明党も8議席にとどまった。これにより与党の非改選議席75を合わせた議席数は参院の過半数125議席に届かず122議席だった。
一方、国民民主党は改選4から17に大躍進し、改選1の参政党は14議席を獲得するなど、野党の躍進が顕著に表れた結果だった。
選挙結果を踏まえて自公両党は、過半数の議席を維持できず衆議院に続き参議院でも少数与党となった事により、石破首相は「比較第1党としての責任は重い」としながらも、総理大臣を続投する意向で、7月21日に正式に表明する見通し。各党の獲得議席は次の通り(カッコ内は順に選挙区、比例代表の議席)。
自民党=39(27、12)立憲民主党=22(15、7)公明党=8(4、4)日本維新の会=7(3、4)共産党=3(1、2)国民民主党=17(10、7)れいわ新選組=3(0、3)参政党=14(7、7)社民党=1(0、1)日本保守党=2(0、2)チームみらい=1(0、1)。
参院選の女性当選者が過去最高の40人
第27回参院選の女性当選者が40人に達し、前回2022年の35人を上回り過去最多となった。選挙区で参政党のさや氏(東京)、国民民主党の牛田茉友氏(東京)らが、比例代表では参政党の梅村みずほ氏、岩本麻奈氏らが当選を決めた。125議席の内の32.0%を占めた。
立候補した女性は152人で前回に比べ29人減だった。全候補者に占める割合は、政府の目標の35%に対し29.1%だった。
女性の立候補者は選挙区に102人、比例代表に50人。政党別では自民17人、立民21人、公明党5人、日本維新の会7人、共産党20人、国民12人、れいわ新選組11人、参政党24人、社民党4人、日本保守党2人。

台湾華僑の重鎮が「政局に影響」「台湾人にも影響」を示唆
第27回参院選挙の結果を受けて、台湾人及び華僑の重鎮からは様々な意見があった。中華民国華僑人の重鎮、詹德薰氏は、日本の自民党が今回の参議院選挙で単独過半数に3議席届かなかったことについて「政局の安定性に影響を及ぼす可能性がある。対台湾政策に変化があるか注目すべきだ」と述べた。「外国人規制」や「日本優先」を政策掲げる野党の台頭については「これは日本社会において外国人資源の利用に対する感度が高まっている事の反映で、日本在住の台湾人に悪影響を及ぼす恐れがある」と警鐘を鳴らした。
「経済の低迷と高水準の債務が続く」とする一方で「政局が不安定になるかどうかは引き続き注視する必要がある」とし「仮に政権がより穏健な立場の勢力に移行した場合、対台湾支援が継続されるかどうかについても、予め備える必要がある」と注意を促した。
なお、今回の選挙で大躍進を遂げた野党は、若い世代をはじめ、SNSの影響が大きく反映された結果とも言える。これにより幅広い世帯からの支持を集め、特に参政党の政策はわかりやすく、世襲制の崩壊も顕著に表れた。

対台湾法案の進展に影響を与える恐れ
星城大学特任教授盧聰明(前副学長)は、参議院選挙において「自民党連立政権が過半数を確保できなかった事が政局の安定や対台湾法案の進展に影響を与える恐れがある」と指摘した。
しかし、国会内には依然として多くの親台湾派議員が存在しており、超党派の協力が推進されれば「対台湾支援は今後も継続される可能性が高い」と強調した。台湾側としては「野党内の親台湾勢力と積極的に連携し、日本の今後の与野党協力の動向や外交・防衛予算の変化に注視していく必要がある」とコメントした。

日本人ファーストは「在日台湾人にも影響」と示唆
新潟産業大学の詹秀娟名誉教授は「アメリカ・ファースト主義」は日本にも影響を与え、参政党が政策に掲げた「日本人ファースト」により、選挙で躍進を遂げ「外国人制限」や「日本優先」が注目されたと指摘。在日台湾人にも影響が及ぶ可能性があると述べた。
少子高齢化の渦中にある日本において「日本は外国人との共存・共生・共栄を目指すべきで、優秀な人材の選別も必要」と強調。また、在日台湾人は「優等生」とし「親台派議員を支援し台湾の国際的地位向上に貢献すべき」と提言した。

野党が大躍進 世襲制にも「ノー」を突き付けた
今回の参院選はこれまでにないSNSを駆使した選挙戦であったといえる。情報の拡散方法が多様化し、街頭演説に加え、これまでの公共放送、各種マスメディアによる情報に新たにSNSが加わった格好でもある。
各政党の政策に関心が高まったのは、こうした新たな情報源が加わった事による影響が高い。裏金問題や減税政策の論議、社会保険、給付金など多岐にわたる目の前の課題があり、それを有権者が情報をもとに各政党の政策を思慮した結果が、野党躍進となったものとみられる。これまでも、世襲政治によるマイナスを訴求してきた有権者は今回の選挙できっぱりと「ノー」を突き付けた。
さらに、投票率も58%を上回ったとの見通しで、これらすべての好材料はSNSの影響を否定はできない。
与党の過半数割れで野党との連携、野党同士の連携、ひいては内閣総辞職なども予見される。日本の将来は確実に変革時期に突入したといっても過言ではないだろう。
2025.07.21