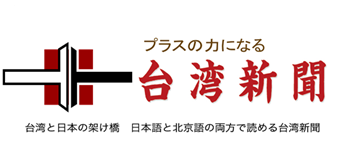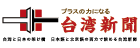【讀者寄稿】『日本経済新聞』は、2025年7月初旬に3日連続でコラムを掲載し、「消える国際秩序」、「武力による解決を黙認する世界」、「中東外交すくむ日本」の各テーマのもと、イスラエルおよびアメリカによるイラン核施設への攻撃と、それに対する欧州や日本など民主国家の反応について、鋭い省察を行った。
同紙は、欧州諸国は低姿勢で対応し、非難の声すら上がらなかった。「国際法と多国間主義」をかつて重んじたヨーロッパにとって、この沈黙は「平和的解決」という原則の揺らぎと受け止められている。
日本もまた、中東へのエネルギー依存と日米安保体制という二重の制約により、身動きが取れずにいる。こうした現状は、単なる外交の曖昧さではなく、むしろ戦略の空白と呼ぶべきだろう。
しかし、民主主義陣営の旗頭たるアメリカは、今回の事態において黙認にとどまらず、明確な関与者である。
2018年にトランプ政権がイラン核合意離脱して以降、一貫して強硬な対イラン政策を維持してきたアメリカは、再登板したトランプ大統領は、即座に軍事行動を取った。その姿勢は、武力を尊ぶ中国共産党の目には、複雑な思いで映ったに違いない。
アメリカはもはや「国際秩序の仲裁者」という立場を取らず、むき出しの実力行使を厭わない。他の民主国家、たとえば欧州や日本の沈黙も、結果的にその姿勢を黙認するかたちとなっている。「力こそ正義」という現実が台頭し、世界の自由陣営における秩序は再構築の只中にある。
一方、専制独裁国家の陣営は機を見て蠢いている。ロシアはイランとの軍事協力を強化し、中国はイランを軸に「脱ドル化」と「脱西洋中心」の戦略を掲げ、国際秩序の書き換えを目論んでいる。
ウクライナ戦争からペルシャ湾の火線、そして南シナ海・台湾海峡に至るまで、世界は複数の対立軸を抱える時代へと突入した。これは単なる軍事競争ではなく、体制と価値観の衝突である。そして台湾は、この民主と専制の対立の最前線に位置している。
台湾は戦略、価値、そしてテクノロジーの世界的中枢である。第一列島線の要衝に位置し、世界最先端の半導体産業を掌握する台湾は、地政学にも経済的にもの観点からも代替不可能な存在であるだけでなく、漢語圏において唯一の自由民主主義体制を築き上げた国家である。
この成果こそが「護国の砦、神の山(護国神山)」となり、専制独裁者たちにとっては喉元の棘となる。自由世界にとっては、まるで宝を抱くかのように大切にされている。
現在、ロシア・ウクライナ戦争の長期化、中東は再び混迷を極める。欧州は沈黙し、日本のジレンマが続く中、台湾の存在感は日増しに高まっている。台湾はもはや辺縁ではなく、最前線であり、「厄介者トラブルメーカ一」ではなく、「自由と民主の価値を守る砦」である。
仮に、自由主義陣営の枠組みやルールが変化しても、台湾の持つ本質的価値が変わらない限り、国際社会は引き続き台湾に向けられるだろう。台湾は危機の象徴ではなく、自由と民主の灯台であり、誰かの手で動かされる駒ではなく、比類なき価値を放つ光源であり、世界の希望を示し続けている。
2025.07.09
大田一博 寄稿