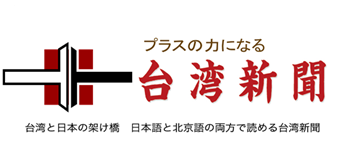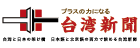【読者投稿】日本のお盆休みを利用して、私は日本から台湾へ渡り、台湾の旅行会社が主催する「地中海クルーズ十二日間の旅」に参加した。総トン数17万5千トン、乗客数4300人を収容する巨大な客船で、欧米の乗客が大半を占め、東洋人は少なかった。
十二日間の航路は、スペインのバルセロナを初発とし、イギリス領ジブラルタル、フランスのマルセイユ、イタリアのジェノヴァを経てローマに至る。南欧四カ国それぞれの文化と歴史が交錯し、独自の魅力を放っていた。
*歴史的紛争と文明の道
バルセロナはカタルーニャ自治州の首府として、古来より列強が争奪を繰り返してきた地である。ギリシャ人、カルタゴ人、ローマ人による支配、さらに近代のスペイン王権へと移り変わり、常に統一と独立の狭間に揺れ続けた。
幾世紀にもわたり、愛憎が絡み合い、情と理が分かちがたく、今日に至るまで独立の声は絶えない。その内面の葛藤は、どこか台湾の境遇に重なるものがある。
ジブラルタルはさらに地政学の縮図である。地中海と大西洋の喉元を押さえるこの地は、古来より兵家必争の要衝。
巨岩に穿たれた迷宮のごとき坑道は、万の兵と一年分の糧食を収容でき、台湾の金門・太武山の坑道を彷彿とさせる。
イギリスとスペインはこの主権をめぐり今なお対立を続けている。
*台湾社会の縮図としての旅行団
今回同行した台湾の旅行団は、まさに台湾社会の縮図であった。四大族群(本省人、外省人、客家人、原住民)を含み、老若男女が揃い、足の不自由な者から元気旺盛な若者、幼い子どもに至るまでが一堂に会した。
台湾人ガイドは専門性と細やかな気配りで旅程を導き、団員同士も自然に助け合い、老を扶け幼を携える孝と慈がそこかしこに溢れていた。
その素朴で偽らざる善行は、日本に住む私の胸を熱くし、台湾という国の無形にして深い「ソフトパワー」を実感させた。
*公務体系の効率と温もり
旅を終えて台湾に戻り、旧友の歓迎を受けた翌日帰日の際、搭乗手続きを終えた後、小さな荷物が紛失していることに気づき、半ば諦めながら桃園空港第二ターミナルのMRT駅で遺失物届を出した。
多忙を極める駅員は辛抱強く耳を傾け、しばし待つようにと言った。すると三十分後には発見の報が届き、さらに四十五分後には「原物返還」が叶った。
雑踏の中で消えた荷物が、わずか七十余分で奇跡のように戻ってきた。その瞬間の驚きと感動は言葉に尽くし難く、まるで世の喧噪と無常のなかに、優しくも揺るぎない光を見たかのようであった。
ヨーロッパ旅行で味わったスリ横行の不安を思えば、台湾社会の明るさと温もりはひときわ際立っていた。公務員の誠実さと細やかさは、専門性を超えて人間味を伝える。その安心と信頼は、深く心に響いた。
なによりも、これが日本の真摰な友好国台湾で起こったことに胸が熱くなり、これこそ、台湾の「ソフトパワー」の最も真実で感動的な証明である。
*文明の差異とソフトパワーの強靱さ
カタルーニャとスペインの統独問題、ジブラルタルをめぐる英西の主権問題。歴史は紛争の連続であったが、自由民主の体制下では対立も文明的に処理され、血を流すまでには至らない。「争えど乱れず」という光景は、まさに民主主義の尊さを示すものだ。
だが台湾が直面するのは非文明の角力である。第一列島線の要に立つ台湾は、自由民主陣営の最前線にあり、独裁専制の恫喝と圧力に晒されている。それは理性の論争ではなく、力による威圧である。
この時、台湾が拠るべきは強靭な「ソフトパワー」──すなわち人民の善良、社会の韌性(粘り強さ)、制度の透明、文化の厚みである。それこそが「『以柔克剛』(柔よく剛を制す)」の力を発揮する。
老子『道徳経』曰く、「『慈故能勇。天將救之,以慈衛之』(慈しみの心があるからこそ、本当の勇気を持つことができる。天が人を救おうとするときは、慈しみをもって守るのだ)」。
ソフトパワーは弱さではなく、「『上善若水』(上善は水のごとし)」という慈心の勇気である。水は至って柔らかく、されど石を穿つ。形なきがゆえに、いかなる堅固をも打ち砕く。この粘り強さの大道の義こそ、台湾が風雨に晒されても揺るがぬ所以である。
*台湾の文明としての勇気
今日の台湾は、銃や砲によってではなく、文明によって世界に立つ。海外での旅の助け合い、国内での公務の効率と誠実、社会文化に息づく善意と慈しみ。それらすべてが、武力を超える無形の力である。
その力は軍艦、飛行機の威勢ではなく、沈黙のうちに人を教化する品格にあり。鉄壁の強制ではなく、心の奥底に宿る自由にある。
ゆえに、台湾が専制の圧迫に直面するとき、硬さで硬さに対抗するのではなく、文明の力をもって応じる。慈心を盾とし、柔徳を矛とする──まさに「備えて戦を畏れず、戦わずして戦を制す」。それこそ台湾のソフトパワーであり、怒濤の中にあって揺るがぬ定海神針なのである。
2025年8月26日
医療法人輝生医院理事長
京都大学医学博士 大田一博敬具