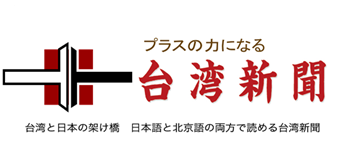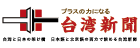【読者投稿】第二次世界大戦終結から八十周年を迎える今、中国共産党は「抗日戦争および反ファシズム勝利」の名目を掲げ、巨額の資金を投じて、華美ではあるが実質を欠いた大規模な軍事パレードを挙行した。
滑稽なのは、終戦当時、中共政権はいまだ建国すらしておらず、日本を打ち破り太平洋戦爭を勝利に導いたのは米国と連合軍であったことだ。中国戦区で日本派遣軍総司令・岡村寧次の降伏を受けたのは、中華民国の何応欽将軍であった。抗戦の主力とは無縁であった中共が、厚顔無恥にも「抗日の中流砥柱(中心的支え)」と自称するのは、次の五つの意図にほかならない。
一、内憂外患を逸らすため
中共は内政の失敗で経済困窮し、民怨が鬱積する一方、「戦狼外交」で周辺に敵を作っている。自らを救うため、軍事パレードを利用して武力を誇示し、国際・国内の苦境から一時的に視線を逸らそうとしているのだ。
二、歴史を歪曲し「一つの中国」を粉飾
毛沢東自身が「抗日の一割、対応の二割、発展の七割」と語ったように、中共の抗戦史実は極めて薄弱である。その真相を隠すため、あえて大規模なパレードを行い、「中流砥柱」という虚構を強調し、歴史の語り口を支配しようとする。その延長に台湾統一の正当性を構築する狙いがある。
三、台・日・米の友情を離間させるため
八十年前、米国は中華民国と肩を並べて抗日し、台湾は日本の植民地として戦火の犠牲となった。今日、中共は援華最深の米国に感謝するどころか、むしろ挑発を重ね、台湾・日本・米国の堅固な友誼を破壊しようと画策している。
四、虚勢を張り軍心を安んずるため
近年、中共軍高層は相次いで失脚し、中央軍委の半数近くが欠員となり、軍心は動揺している。敵を作り、民族主義を煽ることによってのみ体制を立て直そうとしている。その方便こそ軍事パレードである。
五、隙を突き反米同盟を画策
米、中対立、ロシア・ウクライナ戦争、台湾海峡の不穏を背景に、中共はパレードを機に「グローバル・サウス」と称される国々を取り込み、反米同盟を組織し、西側の結束を削ぎ、自らを「米国より信頼できる世界的リーダー」と演出しようとする。
しかし、集まったのはほとんどが後進国であり、西側先進国は一切姿を見せなかった。「反ファシズム勝利」を名目としながら、主賓はウクライナ侵略のロシアと、その共犯である北朝鮮であり、かつての戦勝五強──中華民国、米、英、仏、ソ連(既に解体)──は皆無であった。BBCはこれを「反米同盟の外交パーティー」と揶揄した。
軍部の腐敗を覆い隠すためのパレードであったが、総指揮官の人事異変によって、逆に軍の不安定さが一層露呈する結果となった。「万邦来朝」の気勢を演出しながらも、その実態は外見ばかりで内実は空虚であることが、かえって明白になったのである。
戦争と平和の省察
第二次世界大戦を経験したすべての国にとって、記念の核心は「平和への反省」であるべきであって、「武力の誇示」ではない。老子は言う──「人を殺すに多ければ、哀しみ泣いてこれを弔う。戦勝は葬礼としてこれを扱うべし」と。将軍一人の功の背後には、万骨の枯れる惨状があるからだ。
西洋の文明国が荘厳かつ静謐に戦争を記念し、平和の価値を強調するのに対し、中共だけは逆の道を行き、抗日の仇を政治利用している。
すでに当時のファシズムも軍国主義も自由民主の文明体制に変容したというのに、中共は八十年間、ひたすら「反日教育」で民族主義を煽り、高圧統治を維持してきた。そこに見えるのは、ただ不安と心虚にすぎない。
歴史の教訓
老子は言う──「物壮すれば則ち老いる。これを道にあらず」と。大漢の武帝は好大喜功により衰亡を招き、大清の乾隆帝は「十全武功」によって盛極必衰を招いた。前車の覆るは後車の戒めであり、歷史の教訓は遠からずである。
改革開放以来、中国は「韜光養晦(光を隠し、闇に身を置く)」政策によってやっと国力を蓄えた。だが、いまや多少の成果を得た途端、民生を顧みず武力に執迷し、好戦の道に迷い込みつつある。この歩みはまさに「物極必反(行き過ぎれば必ず逆に転じる)」の古道をなぞり、再び歴史の輪廻に沈もうとしている。その姿は、実に痛惜の念を禁じ得ない。
2025年9月8日
医療法人輝生医院理事長大田一博敬具