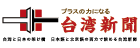台湾人ならではの外交関係への考え方
台湾と82年にわたって正式的な外交関係を持っていた中米ホンジュラスは、3月26日をもって台湾と断交して中国と国交関係を樹立した。これにより台湾が外交関係を維持する国は13カ国となった。
ホンジュラスの続き、南米パラグアイにも不穏な動きが伺がえる。4月に行われる大統領選には、台湾と外交関係を続けるかどうかが争点となっており、現状維持を主張する与党候補と現状変更を掲げる左派候補の間では論戦が繰り返されている。
このような状況において、台湾市民はどう考えているのか。実際に台湾の電子掲示板やSNSの投稿を読めば「物乞いだったらさっさと追い出せよ」「やった!またお金の節約ができた」など、外交状況をあまり心配せず、むしろ断交を喜ぶコメントが多数見つかった。
ではなぜ、台湾人はこういう考え方を持っているのか。
「我々こそ唯一かつ合法の中国政府だ」 中国代表権を巡る激戦
中国内戦に敗れて台湾まで撤退した中華民国(当時=蔣介石政権)は「反攻大陸」をスローガンに掲げ、自らこそ「正統な中国」を国際社会にアピールした。
当時は、米ソ冷戦を背景にして世界が二つの陣営に分かれ、成立したばかりの中華人民共和国はソ連陣営を選んだ。一方、中華民国は一貫して米国陣営に所属し、第一列島線の一環として機能を果たしていたことで、米国の支持を得て国連の中国代表権を保った。それに台北と北京はお互いのことを「反乱軍」と位置付けにし、他国とは相手を承認しないことを条件にして国交を結ぶことになる。
当時世界中に北京当局でなく台北当局を「正統な中国」として承認する国が多く、台湾は中国代表権を巡る論戦において第1ラウンドを勝利していた。
しかし1970年代に入ると、状況が一転して中華人民共和国の優勢になった。中華民国を入れ替わって国連で中国代表となった中華人民共和国に対し、日本を始めとする米国の盟友は次々と国交関係を樹立し、米国自身も1979年に中国と外交関係を築いた。
当時の台湾は工業化を目指しており、毎年二桁の経済成長率を果たしていた。経済面から残りの正式的外交関係を結ぶ国を「金銭外交」にして「正統な中国」を主張し続け、断交された国と実務関係を維持するのが、国際社会の現実に直面した台湾が選んだ道だった。
経済面の実力も逆転 盟友を失っていった台湾
ところで、中国は1980年代から「改革開放」政策を採択し、急速の経済成長を実現した。1989年の「六四天安門事件」で欧米国家から経済制裁を受けても、国際社会では韓国、南アフリカなどと外交関係を締結し、台湾を孤立させていった。
台湾はこの時期、民主化改革を果たし、当時の李登輝政権は「実務外交」を訴求して「金銭外交」を廃止したが、援助金が減ってきたため、金銭的援助は簡単にやめるわけにいかず、その代わりに台湾は各領域の専門家を派遣し、学校や病院などの建設を協力した。
ただ、中国の圧倒的な経済力とは比較にならず、21世紀に入った頃に28カ国と国交を結んでいた台湾は、徐々に国交国を失ってきた。台湾国内ではこの状況を踏まえて論戦になり「いつか失ってもおかしくない国に無駄遣いをするより、そのお金を別のところに使った方がいい」という意見に支持が集まっている。
失った国交国の現状が話題に 台湾「もうお金使いたくない」
一方、台湾の最高研究機構・中央研究院による「断交国の現状調査」報告書が2022年に発表され、台湾と断交して中国と国交関係を結んでいる国の現状を明らかにした。
2007年に外交政策に舵を取ったコスタリカや2008年に中国と国交締結したマラウイなど、台湾を見限った諸国の経済と医療状況は、中国と外交関係を樹立した後にも改善されていないことがわかった。
中国は金銭的援助を誘因に、諸国に台湾を「中国の領土」に承認させて外交関係を樹立する手法を取っているが、肝心の金銭援助の約束が果たされないケースがある。援助金を目当てに中国と国交樹立を図る諸国に「別にお金を援助しなくてもいい」という論理はこうした背景があるからと見られる。
ホンジュラスと国交断絶のニュースも、台湾で一時話題となって野党が与党民進党の外交政策を批判したが、すぐにほかのトピックに取り替わった。台湾人は中国と金銭で外交戦をすることに飽きたのだ。
しかし外交関係を結ぶ国が減っているという事実は、台湾の外交関係に大きな影響を与えている事も無視することはできない。
事実、台湾総統は頻繁に中米、太平洋の友好国家を訪問して「乗り継ぎ外交」を行っている。訪問中に米国空港に留まり、米国政府の要人や国会議員との交流を深め、台米関係の一層盛り上げを図っている。
国交国が減少する事実を真摯に考え、米国との関係性や向き合い方も本気で思慮しなければならない時期に来ているのかもしれない。
(文:ワンワン)